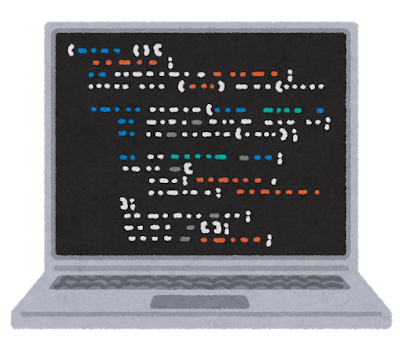
ネットワークのパソコン端末ではLAN間でネットワーク通信を行う場合、常にIPアドレスがDHCPサーバーから振られるか?固定IPアドレスを付けて機器を認識しています。
そのIPを自動的に付与するDHCPサーバーがつながらなくなった場合、ネットワークにつながっているWindowsパソコン端末は、自動でIPアドレスを割り当てるAPIPAという仕組みでIPアドレスを自動で割り当てる。
このようなアドレスを見たことはないだろうか・・・
169.254.2.1・・・・・・169.254.0.0/16
Windowsパソコン端末間は通信できるが、DHCPサーバーとの紐づけができていないため、プロクシなどの外部と通信できるサーバーなどとは通信できなくなる。
DHCPが普及する前の2000年頃には、LAN動詞でパソコン同士を接続させるためにIPアドレスをコンピューターに手動で割り当てることは珍しいことではありませんでした。
2000年を過ぎて一般家庭でDHCPが使われるようになったのは、ISDNやADSLなどのインターネットの常時接続が可能となったあたりからです。
それ以前は、ダイヤルアップ接続が主流だったため、インターネット接続ができるコンピューターは1台のみで、家庭内のネットワーク自体をインターネットに接続することが困難でした。
私は1998年くらいからLINUXサーバーを立ち上げていたと記憶していますが、一般的には自力でLinuxやBSD系OSなどをPCに導入すれば困難ではなかったし、DHCPサーバーも動作させることができましたが、一般的には敷居が高すぎました。
一般家庭でDHCPが利用でき、LANパソコン端末のIPアドレスについて悩む必要がなくなったのは2000年前後で、ISDNやADSLなどにより自宅ルーターなどが入りだし一般消費者のインターネット常時接続が可能になった頃です。
今ではIPアドレスを各パソコンへ割り当てるような面倒な作業を知っているのは、少なくとも50代以上の方ではないでしょうか?
WindowsのTCP/IPには、こうした時代の名残が残っている。それは、自動でプライベートIPアドレスを割り当てる機能でAutomatic Private IP Addressing(APIPA)と呼ばれるWindowsの機能であす。
簡単に言えば、DHCPもなく手動割り当てもない場合に、自動的にIPアドレスを割り当てる機能です。
この機能があるため、WindowsではDHCPがないネットワークにLAN接続でパソコン端末を接続しても、少なくともWindows同士では通信が可能となり、ファイル共有などが利用できます。
APIPAは、169.254.0.0/16の範囲内で自分のIPアドレスを乱数を使って決定します。ただし、IPアドレスのルールとして「169.254.0.0」(ネットワーク自体を示すアドレス)やブロードキャストアドレス(169.254.255.255)は除外します。乱数でIPアドレス候補を決めたら、ARP(Address Resolution Protocol)を使って、そのIPアドレスがすでに利用されていないかどうかを調べます。
今までのことから、IPCONFIGをたたいた時に、この「169.254.0.*」などのアドレスがでると言う事は、DHCP設定にしている場合は、DHCPサーバーとつながっていないことになります。